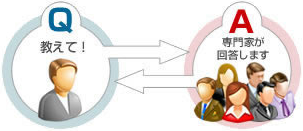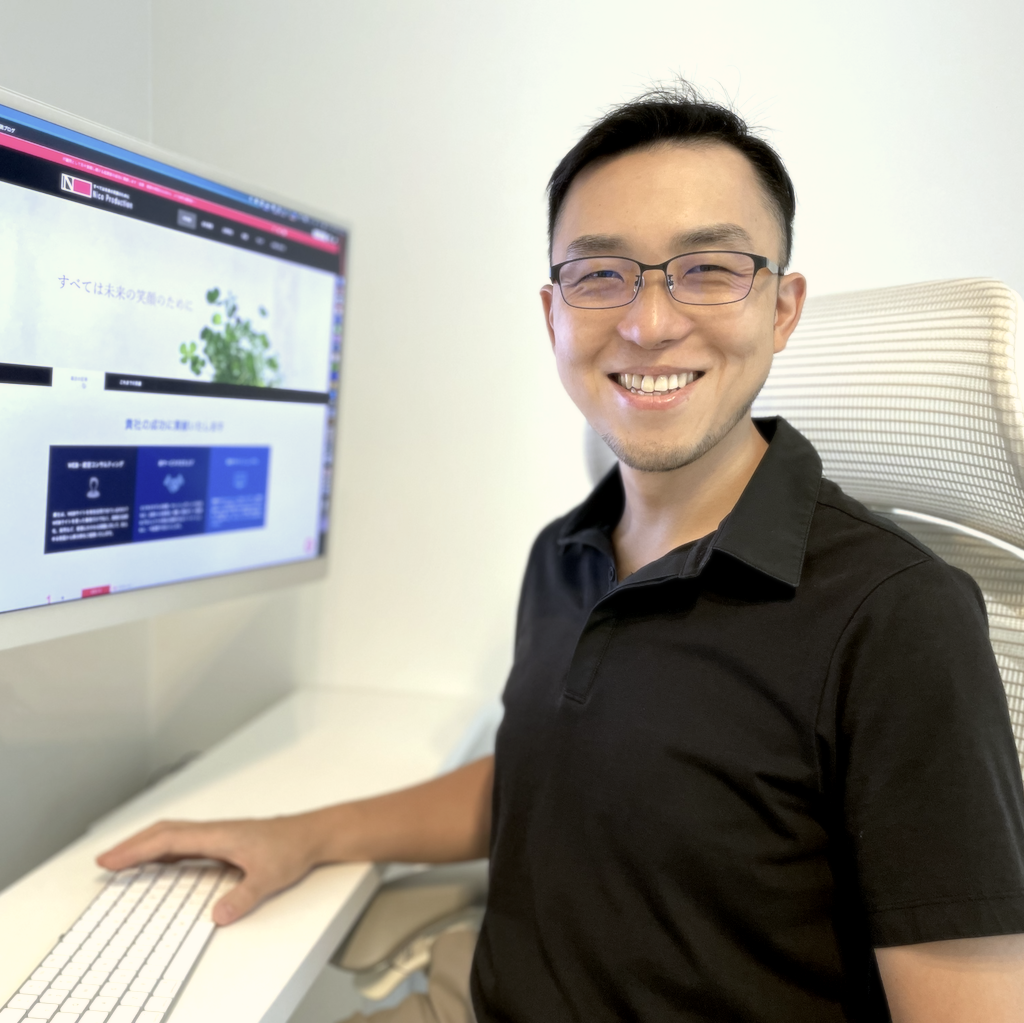起業Q&A 起業に関するみんなの質問投稿サービス
起業に関するみんなの質問投稿サービス 起業Q&A
起業Q&Aとは 弁護士・会計士・税理士・コンサルタント・ベンチャー支援者・起業経験者などの、起業・経営に必要な知識や経験を持つ専門家「ドリームゲートアドバイザー」が、みなさまから投稿された質問に回答するサービスです。
[ 起業Q&A トップに戻る ]
バーチャル・オフィスについて
QUESTION
バーチャル・オフィスをしばらくの間、利用しようと考えています。
会社概要の住所欄にバーチャル・オフィスの住所を記載しても、問題無いでしょうか?
また、メリットとデメリットがあれば教えて下さい。
ANSWER
こんにちは。
アドバイザーの石黒と申します。
「会社概要の住所欄にバーチャル・オフィスの住所を
記載しても、問題無いでしょうか?」ということですね。
この点は問題ないです。
ただし、本店所在地をバーチャル・オフィスにするということで
あれば、登記可能なバーチャル・オフィスかどうかを確認ください。
次に「メリットとデメリットがあれば教えて下さい」ということですね。
この点、メリットとしては
・安価で事務所を持つことができる
・一等地にオフィスを構えることができ、それが信用になる
・電話代行や秘書のサービスが使える場合もある
・郵便の転送サービスをりようできる
・オフィスの間取りにもよるが、利用者との交流が図れ、
場合によっては、仕事に発展することも考えられる。
次に、デメリットですが、
・所在地などでバーチャル・オフィスと分かってしまう場合があり、
顧客によっては、信用の面で取引を控える場合もありえること。
・不在のことが多いとペーパー・カンパニーと捉えられることもある。
以上、参考にしていただければ幸いです。

- 専門分野
- 資金調達 会計・税務
- 保有資格
- 税理士 FP(ファイナンシャルプランナー)
ANSWER
初めまして、公認会計士の高橋と申します。宜しくお願い致します。
ご質問の件ですが、問題がないかと言いますと「問題なしとは言えない」となります。
会社の住所とは本店所在地のことを言い、本店とは会社の主たる営業所を意味します。
営業所の概念について判例は「外部的な営業過程に属する法律行為についてこれを独自に決定施行しうる組織の実体を有することを要する」(最判昭37.12.25民集16巻12号2430頁)としています。
バーチャルオフィスでは、文字通りバーチャル(仮想)なわけですから、通常の場合、判例の営業所の概念には当てはまらず、したがって、本店ではない場所を本店として登記しているということになり、虚偽登記ではないのかという懸念が生じます。
ただ、実際は多くの企業がバーチャルオフィスを活用していまして、これにより大きな問題が生じたというお話は、あまり聞いたことがありません。
以上のとおり、法的観点と実情とをご理解のうえ、バーチャルオフィスの利用をご検討ください。
(上記の回答は平成23年7月現在の法令に基づいております。)
- 専門分野
- 会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
- 保有資格
- 公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士
ANSWER
こんにちは、中小企業診断士の安部一光です。
この度はドリームゲートをご利用頂きまして有難うございます。
バーチャルオフィスは、バーチャルオフィス契約先が認めていれば、
会社概要の住所欄にバーチャル・オフィスの住所を記載しても、問題ありません。
また、下記のメリット、デメリットがあります。
メリット:
・対外的に公開してもよい(自宅ではない)住所を持て、それが信用につながること
・銀座など一等地に会社住所を持てて、それが信用につながること
・業者により郵送物転送サービスを使えること
・業者により打ち合わせ場所などの会議室を使えること
・業者により一時的な執務スペースを借りられること
・業者によりその住所で登記もできること
・業者により電話応対などの秘書サービスを利用できること
など
デメリット:
・お客様がアポなしでいらした場合に不在なので困ること
・業者が倒産や撤退すると、影響を受けること
・見る人が見れば、バーチャルオフィスだと分かること
・業者により最低契約期間が設定されていること
など
利用にあたっては、こうしたことも踏まえ、
総合的に検討する必要があります。
また、弊社では、独りで悩まず一緒に頑張ろう!創業(&経営)相談会を
実施しています。メールでのご相談よりも一回お会いした方が早く多くを
解決できることが多いです。
小職のプロフィールよりお申し込み頂けますので、
ご利用をお待ちしております。
株式会社コマース総研 代表
中小企業診断士 安部一光
http://cir.asia/
TEL045-350-4605
- 専門分野
- 資金調達 経営計画・改善 事業計画・商品開発 研修・コーチング
- 保有資格
- 中小企業診断士 ITコーディネータ / 上級システムアドミニストレータ / 第一種衛生管理者
ANSWER
こんにちは。おぎゅう行政書士事務所、行政書士の尾久陽子です。
会社概要の住所欄に、、、ということは、本店住所も、バーチャル・オフィスの住所で登記されるおつもりということですよね。
バーチャル・オフィスの施設利用契約で、本店登記しても可能とするオフィスは多数あります。
まずは、契約内容を確認しましょう。
メリットとしては、少ない施設費用で、開業ができることです。
デメリットとしては、多くの交流をしておりますと
また、あの住所・・・ということで、
オフィスの住所がバーチャル・オフィスであることが、
おのずとわかることも多いということです。
創業したばかりであったり、新規事業の立ち上げした当初であれば別ですが
架空事務所のような使い方ををして業務上トラブルになっている会社さんが
少なくないともいえ、
中には
オフィスを構えるための信用に足る資金力・事業内容をもっていないのではと
疑問をもたれる方がないとはいえません。
ご自身が進める
事業内容にもよるとは思いますが、
その点は、ご注意されたほうがよいでしょう。

- 専門分野
- 会社設立・許認可 法務・知財・特許 研修・コーチング
- 保有資格
- 行政書士 FP(ファイナンシャルプランナー) CDA キャリアカウンセラー
ANSWER
はじめまして。営業マーケティング担当の本元と申します。1か月前にも同様の相談があり調査を行いましたのでその時点での状況ということでご回答させていただければと思います。バーチャルオフィスの住所を会社概要に掲載することは特に問題ないと思います。借りるレンタルオフィス会社によっては登記上の掲載も可の場合もあります。しかし、許認可や役所に提出する申請書類にはレンタル・バーチャル共に届出上認められず実際の営業事務所での届出しか認められない場合が多くあります。ご質問のお答えになっておりましたら幸いです。

- 専門分野
- 集客・販路拡大・営業戦略 事業計画・商品開発 経営計画・改善
- 保有資格
- 中国前海股権交易中心(深セン)推薦機構正会員 /上海股権托管交易中心(上海)推薦機構授権会員
ANSWER
公認会計士の森 滋昭と申します。
山口さんのおっしゃる通りだと思いますが、メリット・デメリットについて補足させていただきます。
メリットとしては、
・実際にオフィスを借りるより、初期費用・月額費用がかからずに、一等地の住所を利用できる
・電話代行を依頼すれば、外出時に秘書が対応してくれる
・普通のオフィスを借りるよりも、立派な打合せルームを使用できる(バーチャルオフィスにもよります)
・バーチャルオフィスによっては、他の入居者との交流会を行っているところがあり、他の起業家と交流を深められる
・起業家支援として、税理士の紹介や、名刺や販促品の販売等のサービスをしているところがある
デメリットとしては、
・住所は使用できても、法人登記を受け付けない場合がある
・電話対応、打合せルーム、コピー代等のオプション・サービスが、結構高い場合がある
・夜間や休日は使用できない場合がある
・契約期間や、退去時に費用がかかるために、フレキシブルに退去できない場合がある
・郵便物をバーチャルオフィスに頻繁に取りに行く場合などは、結構手間がかかる
バーチャル・オフィスによってサービス内容や料金も異なるので、一概に言えませんが、単に住所が使えればいいと思っても、予想外にオプション費用でお金がかかったり、打合せ等でバーチャルオフィスまで行くケースもあるようです。
しかし、起業時は、初期費用を押さえたいものです。バーチャル・オフィスの場合、なんらかの制約があっても、やはり、通常のオフィスを借りるよりは、リーズナブルです。
いずれにせよ、例えば、
・ご自分のビジネスがどんなスタイルか(例えば、来客するスタイルかどうか)
・今後のビジネス展開どうなるのか(いつ頃通常のオフィスに移るのか)、
こういった観点からもバーチャルオフィスを何件か見て回られるのがいいかと思います。
- 専門分野
- 経営計画・改善 会計・税務 資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可
- 保有資格
- 公認会計士 税理士 中小企業診断士 行政書士 実用英語技能検定1級 / 実用フランス語技能検定3級 / 登録政治資金監査人 / FP(フィナンシャルプランナー)
ANSWER
会社概要の住所欄にバーチャルオフィスの住所を記載しても、問題ないと思います。
バーチャルオフィスのメリットは、なんといっても家賃(料金?)が安いということに尽きると思います。そのため実際にオフィスを借りるとしたら予算的に厳しい場所(銀座や青山など)の住所が使え、信用度が高いように見せることも可能です。
デメリットは、会社の実態がない、又は、ペーパーカンパニーと間違えられる可能性があるということです。ホームページを持っているバーチャルオフィスの場合、住所で検索すれば、一発で見つかってしまいます。その瞬間、会社の信用度合いが落ちる可能性があり得ます。
例えば、高額商品を扱う人が銀座にオフィスがあるとしたら、一見、信用できそうだなと思いますが、それが調べたらバーチャルオフィスだったと分かってしまえば、逆に、信用ならないので、契約しないということがあり得るということです。
オフィスなんて気にしないというお客様もいらっしゃいますので一概には言えませんが、メリットだけではなくデメリットもあるということを知ったうえで利用しないと、ビジネスで一番大事な信用を失いかねないということだけは言えそうです。

- 専門分野
- 事業計画・商品開発 資金調達 会社設立・許認可 経営計画・改善
- 保有資格
- 公認会計士 税理士
- 1
この分野に役立つセミナー
| 事業計画 | |
|---|---|
|
|
|
| 研修資格 | |
|
|
|
| 会社設立 | |
|
|
|