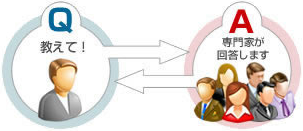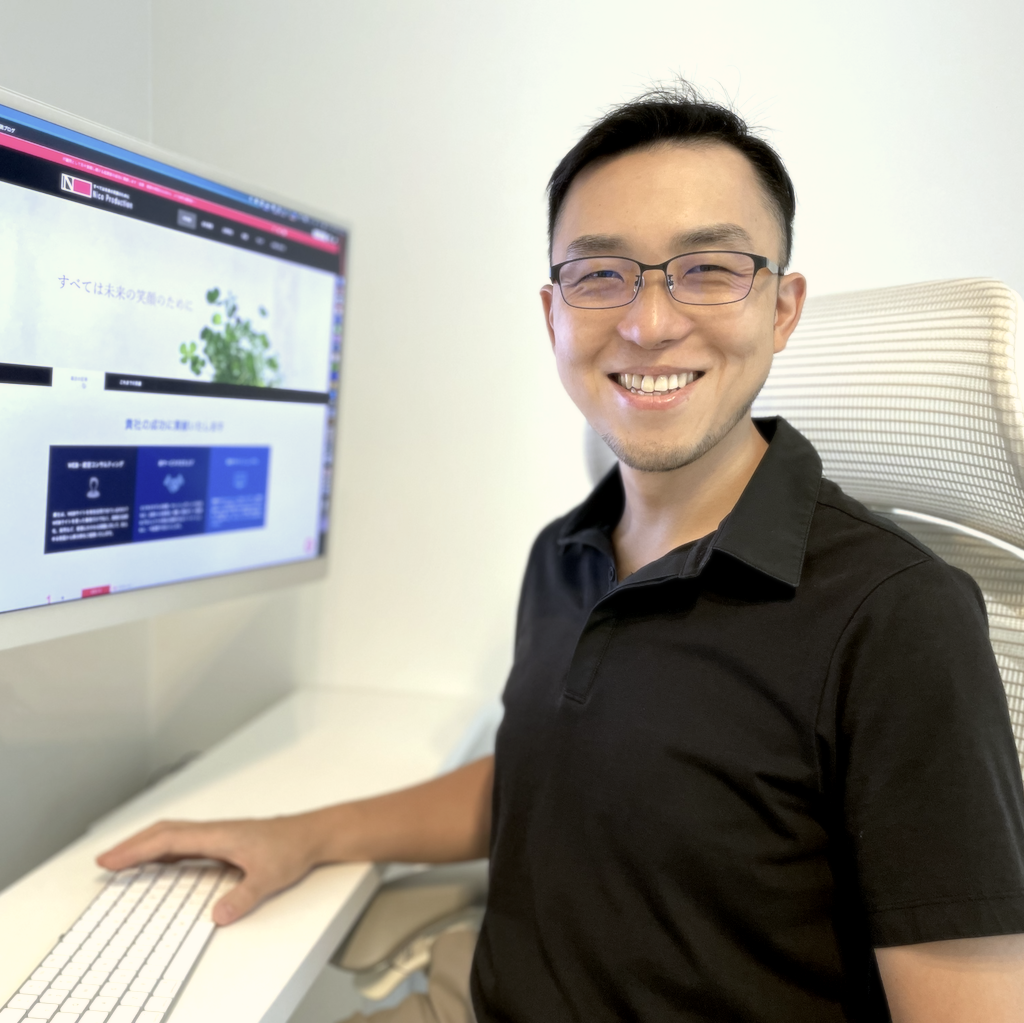起業Q&A 起業に関するみんなの質問投稿サービス
起業に関するみんなの質問投稿サービス 起業Q&A
起業Q&Aとは 弁護士・会計士・税理士・コンサルタント・ベンチャー支援者・起業経験者などの、起業・経営に必要な知識や経験を持つ専門家「ドリームゲートアドバイザー」が、みなさまから投稿された質問に回答するサービスです。
[ 起業Q&A トップに戻る ]
役員社宅の本人負担額について
QUESTION
お世話になっております。
表題の件、
現在、役員の賃貸を社宅化しようと考えております。
そこで役員の会社の社宅手当の金額なのですが
役員の場合は家の床面積に応じて3通りに計算方法が分かれていると言われています。
ただ計算基礎に「その年度の家屋の固定資産税課税標準額」が含まれているため、通常計算できない、という話もインターネット上に落ちております。
私は役員の月家賃8万円のワンルームマンション(8畳)を社宅にしたいだけなのですが
家賃の30%を会社負担、など適当に決めると後々問題がおきますでしょうか?
もし適当に決めていいのであれば何パーセントくらいが相場なのでしょうか?
また士業にご相談するとした場合、どのくらいの予算が必要なのでしょうか?
※普段 士業のお世話になっておらず、自分で決算なども行っております。
その辺りご教示頂ければ幸いでございます。
ANSWER
元国税調査官の公認会計士、田中です。
役員、240㎡を超える等の豪華社宅ではない場合。
賃料の50%か、固定資産税評価額で計算した金額か、いずれか大きい額を、社宅費として負担すればよいです。
通常は、固定資産税評価額で計算した金額がかなり低くなります。
ですので、一般的には、賃料の50%以上を社宅費としていれば、まず問題とならないでしょう。
参考としていただけますと幸いです。

- 専門分野
- 会社設立・許認可 事業計画・商品開発 資金調達 会計・税務
- 保有資格
- 公認会計士 税理士 税理士桜友会会員/登録政治資金監査人 / 第9回環境社会検定試験(ECO検定)合格
ANSWER
税理士望月丈偉です。
役員への豪華社宅の取扱いもありますが、ご質問は一般社宅かと思います。
適正賃料等の計算は、
固定資産税課税標準額による一定率計算と
借り賃の50%とのいずれか高い方と規定されています。
借主さんが、大家さんに固定資産税の課税標準をお尋ねしても・・・
大家さんが教えてくれない場合が多いかと思います。
一般的には、固定資産課税標準額計算より、借り賃の50%負担が多いと思います。
社宅制度は、
①借主が会社契約を前提として、大家さんと賃貸借契約を締結します。
②大家さんへの家賃支払いを、会社が全額負担し、その50%を社長が給与より控除して会社に戻す処理が必要です。
③個人名で、家賃契約の場合は、契約そのものを変更して下さい。
ご質問に中には、会社負担率を30%す少なくされていますので、個人負担が70%負担ですから、上記①の前提でしたら・・・取引は是認されると思います。
もし個人契約のまま会社が30%負担ですと、役員への賞与扱いとなり、法人税の修正になりますのでご注意下さい。

- 専門分野
- 会計・税務
- 保有資格
- 税理士 宅地建物取引士
ANSWER
税理士の佐藤と申します。
まず、会社使用部分がある場合は、床面積割合などで家賃を按分して、会社使用部分を引いて、個人使用部分を算出してください。
この按分については、実態に基づいて合理的に計算することが必要と考えられます。
按分が実態に合っていない場合は、一方から他方への贈与(経済的利益の無償供与)と認定されるケースもあるでしょう。
さて、個人使用部分について、会社負担を何割にするか、ということは、役員報酬をいくらにするか、ということと同じことですから、
会社で自由に決めて頂いて構いません(不相応に高い場合は別です)が、毎月おおむね一定であることが求められます。
たとえば、会社の利益が出そうだから会社負担部分を増やすとか、赤字になりそうだから
個人負担を増やす、というのは認められませんし、
また、とくに他意はなくても、期の途中から会社負担を始めたり、
決算時期に過去にさかのぼって負担を調整する、というのも認められないと考えられます。
通常の役員報酬と同じく、定時株主総会のときにそれを決めて、それを次の定時株主総会まで継続する、ということが必要になります。
(役職の変動や、銀行・株主対策で止むを得ない場合など、期中で増減できる場合は限られています。)
ここまでは法人税の話、ここからは役員個人の所得税の話です。
社宅の会社負担額は、役員の給与ということになりますので、本人の給与に含めて、所得税の計算をすることになります(合算後の額が源泉徴収の対象になります)。
この加算額を計算するのに、「固定資産税の課税標準額」が登場するのですが、
これはそもそも、
元々の支払家賃がゼロであったり(会社所有物を借りている場合)、
特殊事情で世間相場と比較して極端に安い場合などで、
会社負担として加算した部分が利用の実態と比較して少なすぎる場合に、税務署が妥当な額を計算するための基準と解されます。
普通の借り方をした場合は、その家賃の額は妥当なものと考えられますので
それを基礎として給与加算額を計算すれば、それで足りるでしょう。
「固定資産税の課税標準額」を使う計算により、有利になるようであれば、その活用の余地がありますが、
一般の賃貸マンションで、家主から「固定資産税の課税標準額」を教えてもらえる可能性は
あまりないでしょうね・・・
経験則の数字で「えいやっ」とやっておいて、税務調査で指摘を受けるまで放置する、というやり方も
聞いたことはありますが、月8万円の家賃について、そこまでリスキーなことをする意味は
乏しいと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
(追伸)士業の相場のほうは、すみません、情報を持ち合わせておりません・・・。
私個人につきましては、パートさんを雇うよりも安い値段で承っておりますので、
ご検討いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせくださいませ。

- 専門分野
- 事業計画・商品開発 資金調達 会社設立・許認可 会計・税務
- 保有資格
- 税理士 メンタルケア・スペシャリスト
- 1
この分野に役立つセミナー
| 事業計画 | |
|---|---|
|
|
|
| 研修資格 | |
|
|
|
| 会社設立 | |
|
|
|